「初心者向けベースを買いたいけど品質が心配・・」
「安いベースは弾きにくいって本当?」
✔︎この記事の内容
→初心者ならば安いモデルで十分。普通に演奏できます
ベースを購入するときに、初心者セットや値段の安いモデルを選ぼうかと悩むことがあると思います。
ベースの値段は数千円〜数百万円とピンキリで、とても高価な楽器がある一方で本当に安い楽器で大丈夫なんだろうか?と不安になりますよね。

安いベースはやめといたほうがいいとか色んな意見があって悩むよね
結論から言うと、初心者が安いベースを選ぶことは問題ありません。
私自身エントリーモデルなどのベースを何本も触ってきましたが、もう全然弾けます
もちろん安いなりに細かいところを言えば物足りない部分はありますが、それは中級者以上にとっての話で初心者にはほぼ問題になりません。
ここでは、安心して初心者向けベースが買えるように、あえて安いベースの悪いところを説明してみたいと思います。
目次
安いベースと高いベースの違い
そもそもベースの値段は何で決まってくるかを考えることでデメリットが見えてきます。
ベースに限らず何らかの製品の値段は、作るのにかかった材料や手間によって大きく変わってきます。

当然、高級な材料を使ったり、より手間がかかっている方が値段が高くなるよ
ベースの場合、貴重な木材を使ったり、高級なパーツを使ったり、職人の手作業が多くなると高くなる傾向にあります。
✔︎高いベースの特徴
- 貴重な材料や高価なパーツを使っている
- 職人が時間をかけて楽器を作り込んでいる
逆に言うと、安いベースには安価で手に入りやすい材料やパーツが使われており、また出来るだけ手間をかけずに作られているということです。
✔︎安いベースの特徴
- 安価で手に入りやすい材料やパーツを使っている
- 出来るだけ手間をかけずに作られている
値段が安いから多少出来が悪いのは当然・・とはいえ、がっかりするほど悪いわけでもありません。
もう少し具体的にみていきましょう。
安価な材料やパーツは音が悪い?
安価なベースに使われている材料やパーツは本当にダメなんでしょうか。
私の経験から言うと、初心者には十分な品質で問題になることはほぼ無いと思います。
✔︎初心者にとって安ベースが問題ない理由
- 木材の違いは初心者にはわからない
- 同様にパーツの違いもわからない
- 普通に音は鳴るし演奏もできる品質
→上級者には物足りないが初心者には十分
それなりに色々なベースを弾いて良し悪しがわかってきた中級者〜上級者にとっては、安いベースに物足りなさを感じるかもしれません。

違いは確かにある。だけど初心者にとっては些細なもの
ですが良し悪しの基準がない初心者にとっては大した違いは感じ取れないはず。それくらい微妙なものです。
もう少し深掘りして解説していきます。
木材の違いはまずわからない
ベースの材料となっている木材は色々な種類のものが使用されており、それぞれに音の特徴があると言われています。

有名どころだとアルダーとかアッシュ。安いベースだとバスウッドなんかもあるよね
木材の種類によってどれだけ音に違いがあるのかというと、実はそれなりに差があります。
印象としては重く硬い木材のものほど芯のある音。逆に軽くて柔らかい木材のものほどぼわっと広がるようなイメージです。(個人的な感想です。)
材質による音の特徴
- 重くて硬い・・・芯のある締まった音
- 軽くて柔らかい・・マイルドな音
→指板材料も同じく違いがある
それぞれ個性があって面白いのですが、どれも微妙な差なので弾き比べしないとよくわかりません。
これから最初のベースを選ぼうとしている場合にあっては、おそらくどれを弾いても「よくわからない」はず。
初心者ならば、木材の違いは気にすることなく、見た目とか重さで選んでしまって問題ないです。
ピックアップなども普通に使う分には困らない
パーツ類の中でもとくにコストがかかり、しかも音に直接影響するのがピックアップ。
ピックアップの値段も一つあたり1000円程度の激安モデルから、2~3万円もする高級モデルまで色々です。

高いピックアップは中の線を手巻きしているらしい。そりゃ手間がかかる
ミドル〜ハイエンドに搭載されているようなピックアップと低価格ベースに載っているピックアップは見た目は似ていても質の面で差があります。
しかし中価格帯以上のピックアップであっても、音の良し悪しは弾く人の好みによるものなので、ある程度の価格帯以上のものならば評価は人によって様々です。
ピックアップの音の感じ方
- 安いピックアップ・・まあまあ安い音
- 高級ピックアップ・・いい音だけど好みは人それぞれ
高級なピックアップに慣れている人からすると、安いベースのピックアップは物足りなく感じるかもしれません。

といっても音が出ないとか音程がおかしいレベルの問題はないから安心して大丈夫(万が一あったら普通に初期不良)
安物がダメだというのは、良いものを知っているその人にとってはダメなだけなので、比較する基準のない初心者にとってはダメな理由になりません。
むしろ安いから選ぶ、という方が合理的だと思います。
手間がかかっていない=弾きにくい?
高級なベースは職人が時間をかけて丁寧に仕上げています。

ボディやネックの微調整に時間をかけて弾きやすいようにしているよ
一方で安価なベースは工場で大量生産され、流れ作業の中で細かいところまでチェックされていない場合がほとんど。
具体的にどのような部分で差が出るかと言うと、私が経験したもので以下のようなものが見られます。
✔︎安いベースの品質の差
どれも致命的にダメなわけじゃない微妙な悪さ加減。状態によっては最悪自分で直すことも出来る場合もあります。
1 塗装の割れや傷
安いベースは最初からボディに傷があったり、塗装が剥げていたりすることが普通にあります。
新品のベースに傷がついているのはショックかもしれませんが、ベースは少し使っていれば傷がついて当たり前のもの。

何回か持ち出せばいつの間にか傷がついているもの。遅いか早いかの違い
フレットなど弦が触れるところに傷がなければセーフです。安ベースとはいえ経験上そこまで酷い状態のものは見たことがありません。
2 フレットの処理があまい
フレットは長い金属の材料をカットして使用しています。
材料を切ったままだと切り口が鋭く危険なので角を丸めるように削る作業を行い、左手の動きの邪魔にならないように形を調整します。

初心者用とかの安いベースだとこの処理があまくて微妙なことがある
低価格ベースでももちろん処理は行われていますが、細かい微調整はされていないことがあり多少の弾きにくさに影響する場合があります。
3 ネックの角の処理もあまい
ネックの形状、とくにフィンガーボードの角部分の丸め処理も弾きやすさに影響するポイント。
フレット同様に細かい調整がされておらず、微妙に弾きにくい仕上げになっていることがあります。

ネック形状については好みでしかないので、自分の感覚がすべて
角の丸め具合はネックの幅や厚みなどと同じで好みでしかなく、自分の好みにあったネックを探すことが大切。
私が今使っているベースもほぼネックで選んでいると言っても過言ではありません。
4 電装キャビティ部に木屑、配線が雑
キャビティとはボリュームやトーンの配線がある内部のことです。
普段は開けないところなので自分で改造やメンテナンスをしない限りは内部を見ることもないでしょう。

低価格ベースはここに加工時の木屑が残ってたりする
木屑が残っていることで音や演奏に影響はありませんが、品質のレベルがよくわかるポイント。
また配線が雑だと配線の半田が取れたりして音が出なくなるトラブルが起こる可能性がありますが、簡単に修理ができますのでそれほど心配することではありません。
初心者セットはこんな人にオススメ
以上を踏まえて初心者セットをオススメできるのはこんな人。
✔︎初心者セットをオススメしたい人
- 初めてベースを購入する
- 予算が少ない
- 正直長続きするかわからない
→初心者だからこそ初心者セットがおすすめ
これまで紹介した通り、初心者ベースの問題点はある程度良し悪しがわかる人にとってのデメリットで、完全初心者には気にならないものばかり。

ちょっと乱暴な言い方だけど、よくわからないうちは問題にならないです
アンプやシールドがセットになった初心者セットもあって、普通に考えてコスパがいいので何を買えばいいのかわからないならば初心者セットの中から好みの色や形のベースを選べばOKです。
楽器を初めても長く続く人は案外多くないので、長続きするか心配ならばなおさら安いモデルにしておいた方が良いとも思います。
少しでも安心したいなら大手楽器店で買う
楽器を購入するのは大手の楽器店がアフターフォローもしっかりしていて安心。
✔︎大手楽器店の特徴
- ラインナップが多く選びやすい
- 品質がしっかりしている
- アフターフォローも対応してくれる
大手の楽器店は品揃えも良いですが、初心者向けセットに力を入れていることが多いのでお得に一通りの必要なものを購入できることが多いです。

こだわり派はもちろん個別に機材を選んでいってもOK
有名どころだとイケベ楽器やイシバシ楽器あたりがオススメなので、まずはネットショップを眺めてみると気に入ったモデルが見つかるかも。
まとめ【ちょっといいベースは2本目に買おう】
色々とダメなところを挙げてみましたが、どれもちょっとずつ悪さはするものの全然弾けないほどのものではありません。
✔︎初心者セットのデメリット
- 安価な材料やパーツで作られている
- 仕上げがあまい
- 最初から傷がある場合がある
→最初のベースとしてなら必要十分
それなりに色々なベースを弾いている人であれば、「あれ、ちょっと弾きにくいな」と感じるでしょうが、とくに初心者であればまず気にならないでしょう。

私も何本も初心者ベース触ってるけど、本当に普通です
国内で流通しているものであれば、全く弾けないようなものは無いと思いますので安心して初心者セットや激安ベースを選んでもらいたいです。
だんだん上達してくると必ず2本目の楽器が欲しくなりますので、そのタイミングでワンランク上のベースを色々と試奏してみると良し悪しがわかってくるかもしれません。
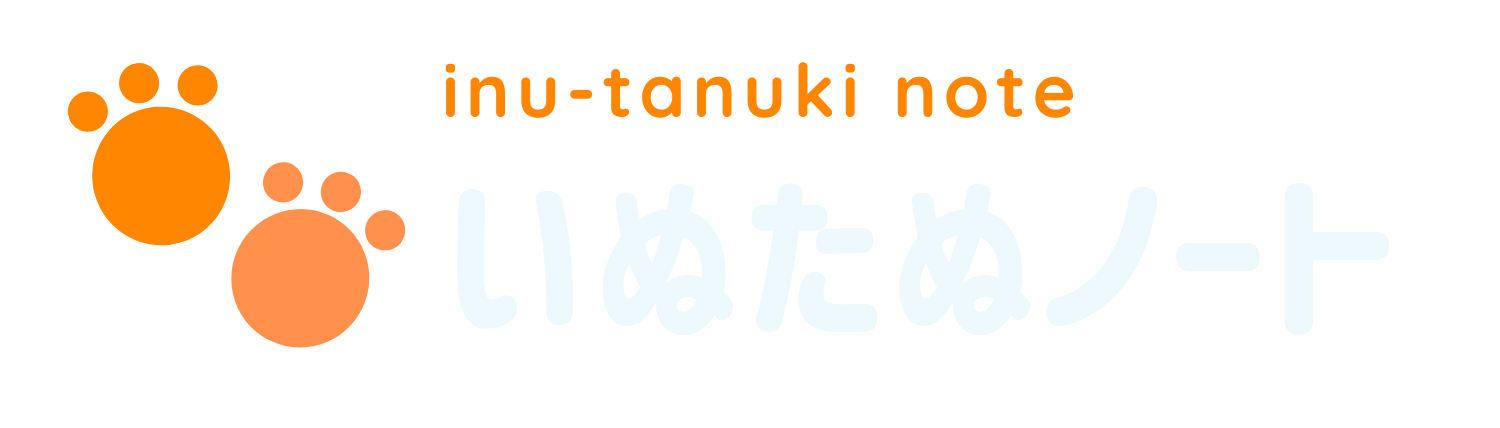
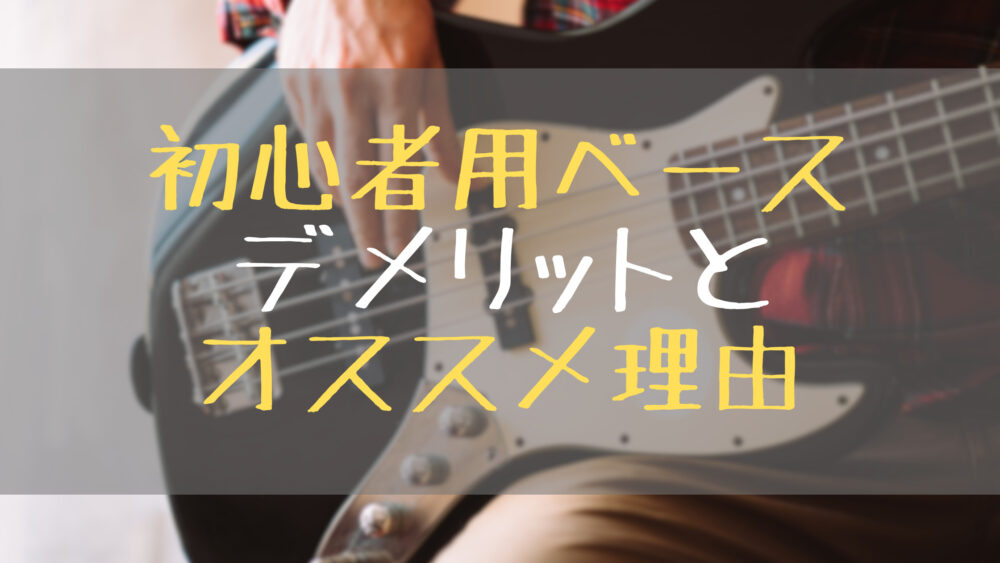
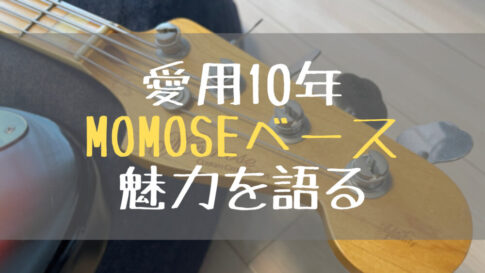

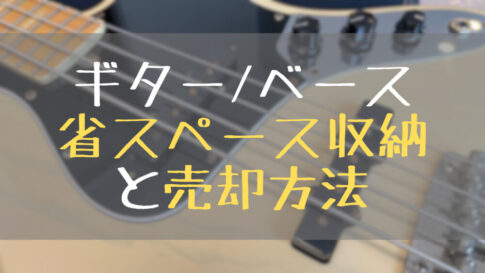

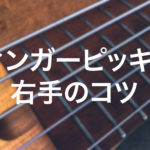
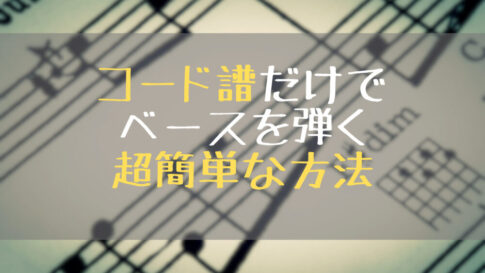
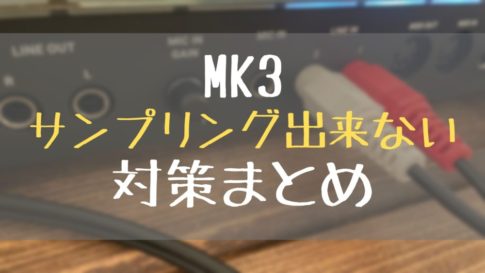



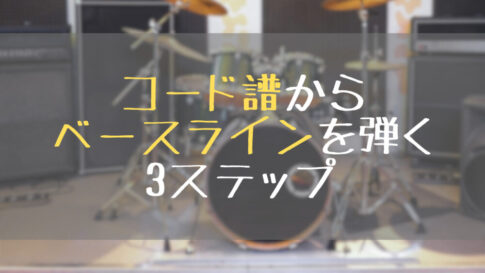



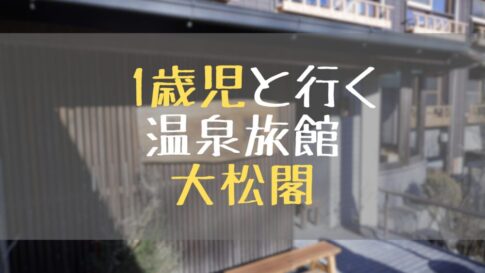
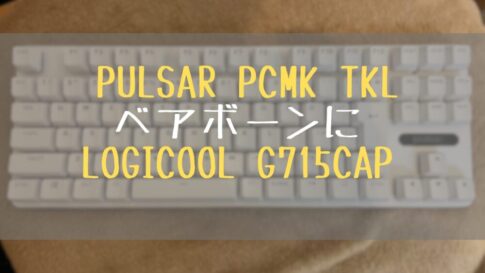



初心者ならば安い初心者用ベースで十分です。ダメだと言われている理由を解説します