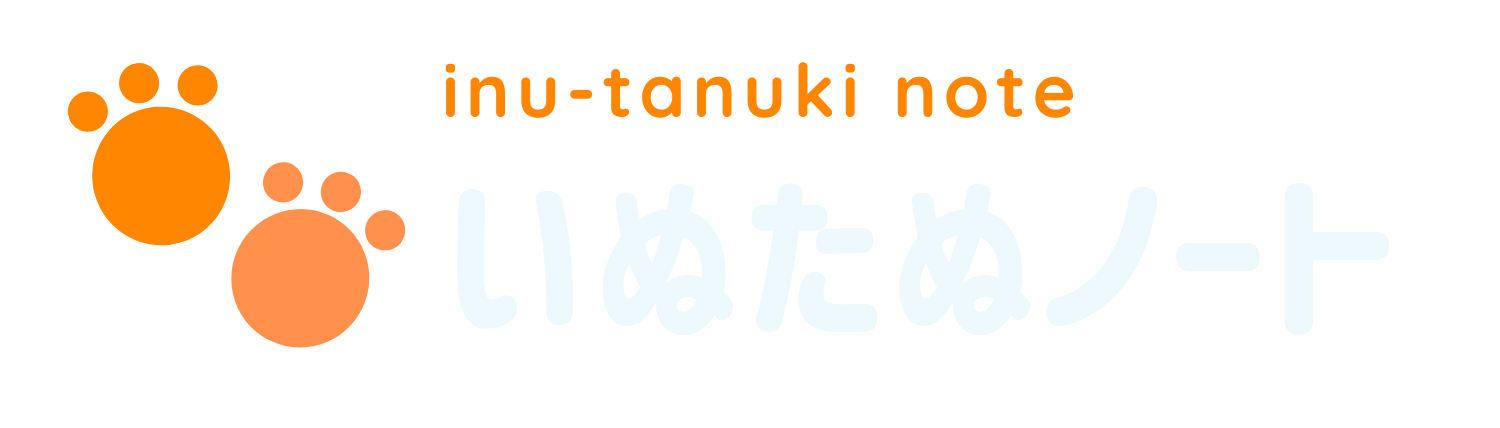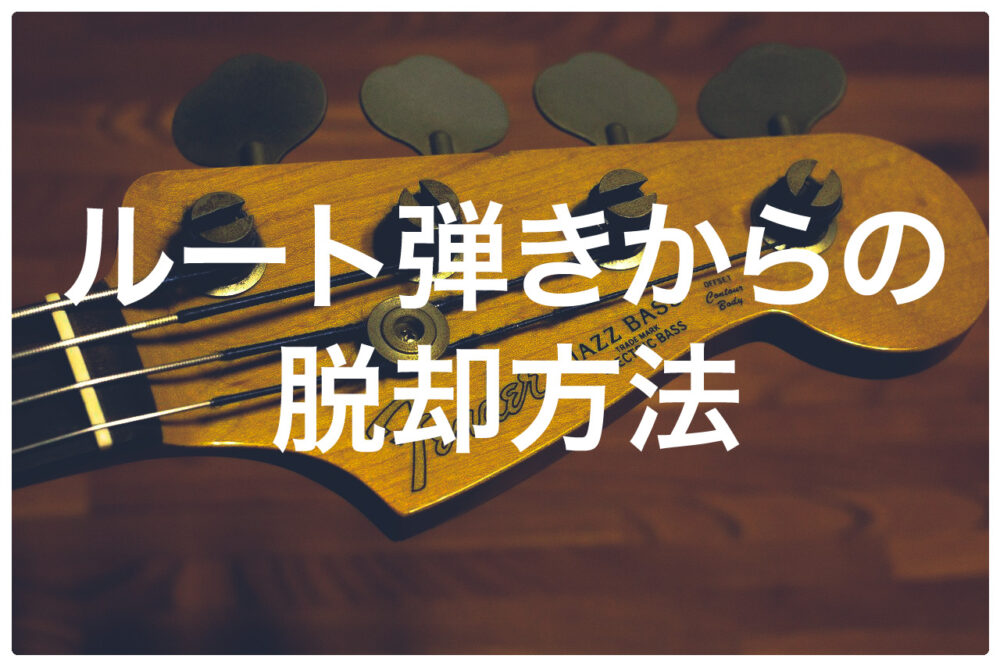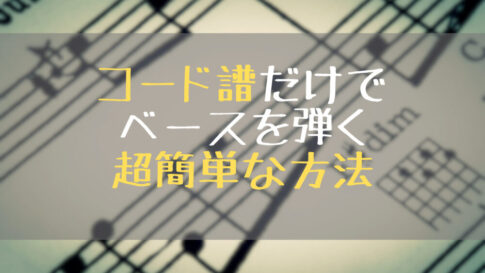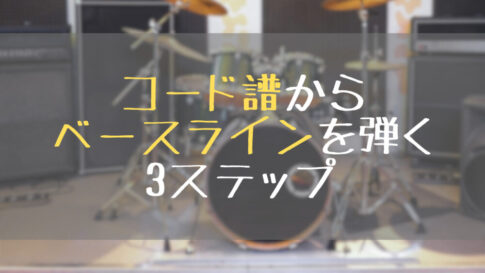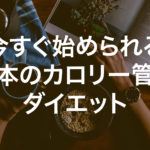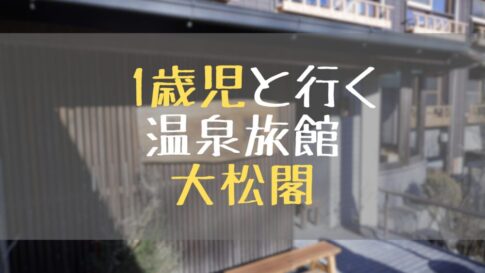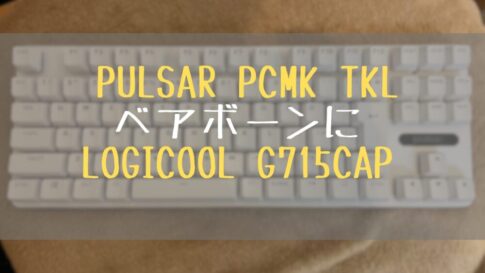ルート弾きからルート以外の音を含めたベースラインへステップアップするための方法についてわかりやすく解説していきます。
- ルート弾きしかできない
- ルート以外の音も入れてフレーズを作りたい
- 音楽理論に興味がある
ルート弾きから脱却するためには、ほんのちょっとコードの知識が必要です。
この記事で全てを説明はできませんが、どこから手を付けていくべきかのヒントになれればと思います。
ルート弾きのおさらい
そもそもルート弾きの「ルート」とはなんでしょうか。
これを理解するには、コードについての知識が少し必要です。
コードとは日本語で和音と呼ばれるように、音の和、つまりいくつかの音を同時に鳴らした音の塊のことを言います。
コードの中で最も音程の低い音をルートと呼び、コードの響きにもっとも大きな影響を及ぼす重要な音です。
ルート弾きのメリット
ルート弾きのメリットは、演奏のしやすさに関する技術的な面と、音の響きに関する音楽的な面があります。
技術的なメリット
ルート弾きは、コードのルート音のみを演奏する方法であるため、楽曲中に同じコードが続く限り基本的には同じ音を鳴らし続けます。
そのため、左手のポジションチェンジが少なく、またピッキングを行う右手側も機械的に同じ動作を繰り返すことが多くなるため比較的演奏のしやすい方法となります。
音楽的なメリット
コードの中の一番重要な音を鳴らすため、バンド演奏全体のコード感をしっかりと支えることができます。
ベースがルートを鳴らしていれば、ほかの楽器が多少間違った音を出しても演奏が崩壊するほど致命的なミスにはなることはすくないでしょう。バンドの底を支えるまさにベースの役割をしっかりと果たせるのがメリットです。
ルート弾きのデメリット
メリットがある一方でデメリットもあります。同じように技術面と音楽面から見てみましょう。
技術的なデメリット
ルート弾き自体に技術的なデメリットはないと思いますが、ポジションチェンジや運指が少ない分、演奏者自身が複雑な運指のフレーズや弦をまたぐフレーズが苦手になりがちです。
ルート弾きしかできないとお悩みの方は、もっと動き回るフレーズを弾いてみたいと思っているのではないでしょうか。これから脱ルート弾きのヒントを記していきたいのでぜひ参考にしてみてください。
音楽的なデメリット
ルート音が続くため、どうしても単調になりがちです。
音楽的にはどっしりと安定したサウンドになり安心感が生まれますが、安定感は行きすぎると退屈に変化します。
聞いていて面白い、かっこいい音楽には緊張感というスパイスが効いてこそ生まれてくるものです。
まずはコードチェンジにちょっとしたオカズフレーズを入れるなどして、演奏に変化を加えていくことで安定感と緊張感を同居させた演奏をつくっていくことできます。
ルート弾きから脱却する方法
ここからはルート弾きから脱却するためのヒントをまとめていきます。
一つ一つについて詳細には説明ができませんので、リンク先などを参考にしてみてください。
コードについて理解する
コードを理解することが大切な理由
ルート弾きから脱却するためには、コードの知識が必要不可欠です。
なぜならば、ルート弾きではない動き回るフレーズは、ほとんどがコード理論やスケール理論に基づいて演奏されているためです。
曲には予め定められたコード進行があり、バンドのメンバーはこのコード進行に沿って演奏を行っています。
でたらめに演奏してもコードから外れた音を弾いてしまうと間違ったように聞こえてしまいますし、お気に入りのフレーズも元の曲と違ったコード進行で演奏すると不協和音と化してしまいます。
コード理論などは一度身につければ、ほかの曲などでも応用ができるので、よく知らない曲でもコード進行さえわかれば安易と演奏することができるようにもなれます。大きな武器になるのでぜひ覚えたいものです。
ベーシストにとってコードは難しくない
コード理論などと難しそうに言われると思わず拒否反応が出てしまうひとも多いでしょう。
コードはものすごい数の種類があり、コードブックをみて投げ出したことがあるひともいるかもしれません。
確かにコードの種類はとてつもなく多いので、全てを覚えようとすると非常に大変ですが、コードの仕組みを理解してしまえばとても簡単に覚えることができます。
この話はこちらの記事にまとめてありますので参考にしてみてください。
コードからベースラインを組み立てる方法
コードについてある程度理解ができたら、実際にコードからベースラインをつくっていきます。
詳細はこちらの記事に3STEPにてまとめてありますのでご参考ください。
STEP1 ルートと5度音で弾く
コードの中でもっとも重要なルート音と、ルート音と最も相性のよい5度音を使って演奏する方法です。
小節の最初は、コード感を出すためにルート音を鳴らし、あとは5度音を交えながら弾くというものです。
STEP2 経過音でコードチェンジを繋ぐ
次のコードの半音上か下の音を経過音といい、コードチェンジの直前に入れることで音のつながりをスムーズにすることができます。
次のコードの半音上か下、なので覚えるのも簡単。それでありながらとても実用的でものすっごく便利な音です。
STEP3 3度,7度の音を入れる
コード音の3度と7度の音を使ってフレーズを作る方法です。ルート、5度、経過音にさらに音を加えたいといったときに便利な音たちです。
ここまで自由に使えるようになればコードを見ただけで自由にベースラインが組み立てられるようになるはずです。
いろんな曲からフレーズのヒントを盗む
コードを勉強して使える音がわかっても、フレーズに落とし込むアイデアがないと中々いいベースラインはつくれません。
そういうときは、片っ端から曲を聴きまくって気に入ったフレーズを盗むのが手取り早いです。
ただし注意が必要なのは、フレーズをまるまるパクるのではなく、アイデアを盗むイメージが大切です。
そのままコピーするだけだとその形に固執してしまいがちで応用の幅が狭くなります、ざっくりとアイデアを盗むくらいにしておくと色々工夫の余地が出てくるのでオリジナリティをもったフレーズに進化させやすくなります。
コードがわかるとベースがもっと楽しくなる
コードをみて自由にベースラインが作れるようになるとベースが今まで以上に楽しくなります。
よく知らない曲でも譜面があればとりあえず弾けますし、アレンジを変えて演奏するなんてことも可能です。
ルート弾きから脱却してコード弾きへチャンレンジしてみましょう!