「コード譜からベースラインが作れるようになりたい!」
「ルートしか弾けなくてどうしたらいいの・・」
✔︎この記事の内容
コード譜だけでベースを演奏してしまうのって何だかカッコいいですよね。
決められたフレーズがなく、コードの中で自由に演奏するのはとても楽しいものです。
しかしコードはとっかかりが難しく、ネットで調べて記号の意味や構成音は出てきても、実際にどうやってベースラインに落とし込むのかは中々わかりにくい問題があります。

知識と経験が必要で感覚を掴むのが難しい
今回、知り合いのベーシストに同じような相談を受け、私の弾き方を教えてみたところ少しの時間でベースラインが組み立てられるように。
同じような悩みを持つ方に向けて、コード譜を読むきっかけになれば幸いです。
基礎知識:コードの構成音を理解する
コード譜で演奏するためには、構成音はわかっておきたいところ。しかしコード種類が多くて覚えるのが大変。
そこで、コード記号の意味から構成音を知る方法を紹介します。
✔︎コード構成音の確認方法
この辺りは一般的な話なのですでにご存知の方は読み飛ばしてOK。
Ⅰ〜Ⅶ度表記について
コードを理解する上で、度数表記は必須の知識です。
度数とは、ルートから見て何番目の音かを数字で表す表記方法です。
度数表記とは
- メジャースケールの音を1〜7の番号で表したもの
- 3度、5度のように表記する
たとえば、キーがCの場合ではCメジャースケール(ドレミファソラシド)のそれぞれに番号を振る形になります。
| ド | レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ | ド |
| 1度 | 2度 | 3度 | 4度 | 5度 | 6度 | 7度 | 1度 |
度数表記にすることによって、キーが変わってもルートからの相対的な音の距離で表せるメリットがあります。

キーが変わると構成音も変わるので、数字で表せられるのは便利
トライアド(3和音)について
コードは3つの音から構成されるトライアドを基本に考えると理解しやすいです。
ルートからスケールの音をひとつ飛ばししたときにできる3つの和音がトライアドで、Cメジャースケールの場合はド、ミ、ソの3つ。
| ド | レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ | ド |
| 1度 | 2度 | 3度 | 4度 | 5度 | 6度 | 7度 | 1度 |
ここで、ドミソがCメジャーコードになるのですが、重要なのはそれが1度、3度、5度で構成されているということ。

コードは度数で考えるのが楽。ドミソもキーが変わると別の音になっちゃう
コード記号の意味から構成音を把握する
メジャーコード(1度、3度、5度)を覚えれば、あとはここから音をずらしたり足したりするだけで、複雑なコードも全て理解できます。
ずらしたり足したりの指示はコード記号を見ればわかるようになっています。
| 記号 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| m | マイナー | 3度を半音下げる |
| -5 | フラットファイブ | 5度を半音下げる |
| 7 | セブンス | 7度を半音下げた音を加える |
| △7 M7 | メジャーセブンス | 7度の音を加える |
| add9 | アドナインス | 9度(2度のオクターブ上)の音を加える |
| 11 | イレブンス | 11度(4度のオクターブ上)の音を加える |
| 13 | サーティース | 14度(6度のオクターブ上)の音を加える |
| dim | ディミニッシュ | 3度と5度を半音下げる |
例えば、Cm7(-5)の場合、Cメジャー(1度、3度、5度)を基準として、3度を♭、5度を♭、7度の♭を追加することで構成音が完成します。

複雑なコードも一つずつ記号の意味を確認すればすべて構成音がわかる仕組みになってるよ
これで複雑そうに見えたコード記号も、どんな音が使われているかがわかるようになりました。
例えばキーがFになった場合でもルートのFを1度としたメジャースケールを考えて、同様に考えればよいだけです。
コードを見てベースラインを組み立てる3ステップ
ここまで基礎知識が整理できたらいよいよ実践。
コード譜面を見てベースラインを弾くためのステップを3段階でまとめていきます。
✔︎コード譜からベースラインを組み立てる3ステップ
ステップ2のところで経過音という新しい考え方が登場しますがしっかり説明していくのでご心配なく。

経過音は簡単&便利なテクニックなので一緒に覚えよう
STEP1 ルートと5度で弾く
コードの中で一番重要な音がルート。ベースラインの基本もルート音です。
ルート音と5度の使い方
- 小節の頭はルート音を弾く
- コードが変わったときもルート音
- 5度はいつでも使える万能音
ルート音はコードを決定づける力をもった強力な音なので、小節の頭やコードの切替わりに鳴らすことで、今この時のコードを明示的に示す効果があります。
私たちは無意識のうちに小節やコードチェンジのタイミングにルート音が鳴ることを期待しており、期待に応えることで気持ち良い演奏と感じてもらえます。

逆にルート音が鳴らないと期待を裏切られた=違和感のある演奏に聞こえる
極端なことを言うと、すべてルート音だけでもベースラインとして全然普通に成り立ちます(いわゆるルート弾き)。
例えば↓みたいなベースラインでも全然OK。※R=ルート。雰囲気で読み取ってください
|RRRR RRRR|RRRR RRRR|RRRR RRRR|R – – R – RRR|
しかしずっとルートばかりでは面白みがないので、ここからちょっと音を増やしていきます。
5度の使い方
ルートだけだと味気ないと思ったら、5度を入れるとお手軽にバリエーションが増やせる。
5度を入れるタイミングとしては、小節頭とコードチェンジのタイミング以外ならばどこでもOK。
ルートと5度は親和性がとても高く、適当に組みわせてもそれっぽく聞こえるはず。
例えば、以下のようなベースラインなんてどうでしょうか。
|RRRR 5555|RRR5 55R5|RRRR 5555|RRR5 – 555|

なんかありそうなベースラインになった気がしませんか
このようにルートと5度だけでも、十分にベースラインが成り立ちます。
コード譜でベースを弾く一番のポイントといっても過言ではなので、まずはここから練習してみるのが良いと思います。
色々な音を使うジレンマ
いろんな音を使ってカッコいいフレーズを弾きたいところですが、あまり色々弾きすぎると落ち着きのないベースラインになりがち。
まずはルート5度でどっしりとした基盤を作って、味付けとして音を足すイメージがおすすめです。
あえてルート以外から演奏するテクニック
上級テクニックとして、コードチェンジの際にルート以外の音から弾き始めることで、期待通りに進まない=何がくるかわからない緊張感を演出できます。
効果的に使うためには、ルート以外のどの音を弾くかとても重要で経験とセンスが問われますが、ハマればとてもクールな演奏になるかも。
やりすぎると演奏全体のコード進行が崩壊し、台無しになってしまうので要注意。

参考までに紹介したけど適当にやると崩壊するのでやめましょう
STEP2 経過音でコードチェンジをスムーズにする
ルートと5度だけでもベースラインになりますが、次はコードチェンジをスムーズにすることを考えます。
そのために使えるのが経過音というテクニック。
経過音でコードを繋ぐ
- コードチェンジの直前に次のコードの半音上or半音下の音を入れる
- 経過音は短い音符でさりげなく入れる
例えばC→ Em へのコードチェンジの場合、次のコード=Eの半音上 or 下を短い音符で入れると、
|CCCC CCCC|EEEE EEEE| → |CCCC CCCE♭|EEEE EEEE|
このようにE♭を入れることで音が繋がりスムーズなベースラインになります。

1音入れただけで全然スムーズさが違って聞こえると思う
ルート、5度、経過音のベースライン
たった3つの要素だけですが、これだけでベースラインが作れることを見ていきます。
例として、C→Am→Dm→G7のコード進行で考えていきます。
例) |C |Am |Dm |G7 |
まずはルートと5度だけで簡単ラインを作る。
|CCCC GGGG|AAAA FFFF|DDDD DDAA|GGGG DDGD|
(|RRRR 5555|RRRR 5555|RRRR RR55|RRRR 55R5|)
ここでCとかGはコード記号ではなく短音と捉えてください。(C=ド)
次に経過音を入れます。入れるのはコードチェンジの直前です。
|CCCC GGGA♭|AAAA EEEE♭|DDDD DDAA♭|GGGG DDGB|(Cに戻る)
(|RRRR 555経 |RRRR 555経 |RRRR RR5経 |RRRR 55R経|)

経過音がはいることでコードチェンジがスムーズに聞こえる
ここでは解説のためにすべてのコードチェンジで経過音を入れましたが、実際の演奏ではときどき入れるくらいでも十分効果的。
ちなみにR→5度への移動の際にも使えるので、R→経→5みたいな動きも可能。
ただし経過音はコード構成音ではないので長い音符で弾くと、違和感があるので注意。
ルート、5度、経過音でベースラインはほぼ完成
とてもシンプルですが、ルート、5度、経過音でだいぶしっかりしたベースラインが作れます。
ジャムセッションとかならばこれだけで大体乗り切れるはず。

かならずしもコードトーンを全て使う必要はなくて、ベースにとって重要なのはこのへん
とはいっても3音だけだと、やはり同じようなベースラインになってしまうので、、
もっとバリエーションを増やしたい!思うようになったらいよいよ3度7度のコードトーンを組み込んでいきます。
STEP3 3度7度でコード感を加える
これまででてきたルート、5度はコードの土台となる音でした。
コードの特徴は、メジャーorマイナーを決定する3度音や、4和音時の7度音などによって印象付けられます。
これらをベースラインに組み込むことで、さらにコードトーンに合った響になりつつ、音の種類が増えてバリエーションが作れます。

もちろんadd9なら9度音だし、コード記号にあった音を組み込むよ
それでは3,7度を使ったベースラインの考え方を紹介します。
3,7度を使ってフレーズを入れてみる
今までのルート、5度、経過音に加え、曲中の要所要所で3、7度をつかったフレーズを入れてみます。
具体的な使い方としては小節の頭はルート、終わりは経過音で固定で良いので、その間の空間を5、3、7度(+ルート)を使って埋めて行きます。
例) |C |Am |Dm |G7 |
|C – CC CEGA♭|A – AA CCEE♭|D – DD FFAA♭|G – GG GFDD♭|(Cに戻る)
(|R-RR R35経 |RRRR 535経 |RRRR 335経 |RRRR R75経|)
4小節に無理やり詰め込んだので弾きにくいかもしれませんが、イメージこんなかんじ。

3,7度音もたまに入れるくらいでちょうどいい
いろいろとパターンを試してみて、気に入ったフレーズをストックしてここぞという場面で使えるように練習しておこう。
歌物ならベースラインはおとなしく
セオリーとして、歌がメインの曲はベースラインは大人しめ(あまり音数を入れすぎない)の方が演奏がまとまります。
歌を聞かせたいのにベースがうるさいと色々とぶち壊してしまいかねないので要注意。

いろいろ弾きたくなるけどグッと我慢
サビなどの盛り上がる部分だけ、ちょっと音数多めのフレーズを入れて盛り上げていきましょう。
うねるベースラインが作りたいなら積極的に音数をふやす
逆にベースラインが縦横無尽に走り回るような曲、うねるベースラインを作りたいならば、積極的に音数を入れていく方法が有効です。
その場合でも、小節頭はルートのルールを崩さずにコードの流れを全体に示しながら、うまく間にフレーズを入れていくことになる。

ルート音がなくなると全体のコード感が失われるのでほんと注意
音の繋がりが重要になってくるので、3,7度音に対しても経過音で音を繋いでスムーズなラインを目指そう。
番外編 スケールを使ってフレーズのバリエーションを増やす
コードトーンを入れてもまだ物足りないならば、スケールを使うことも可能。
ただしスケールはコード進行を踏まえて選んでいかないと、バンドアンサンブルと違った音づかいになってしまうので注意(結構難しい)。
ここでは詳しく紹介しませんが、コードとスケールの関係から調べてみることをおすすめします。
まとめ【コード譜からベースラインはつくれる!】
以上、コードの読み方からベースラインへの落とし方について紹介してきました。
✔︎コード譜でベースを弾く方法
かっこいいベースラインを作ろうとすると、ついつい音数を増やしてしまいがちですが、一番重要なのはルート5度。

ポップス演奏しようと思ったら7割くらいルート5度だと思う
ちょっと地味かもしれませんが、基本と思ってやってみてください。飽きたら他の音も足していけばOKです。
以上でおしまいですが、この話を知り合いの初心者ベーシストに説明したところ1時間くらいでそれなりにベースラインが弾けるようになったので、結構効果あると思います。
個人的な理解をもとにまとめてますので、他解説と食い違いあるかもしれませんが参考程度にお願いします。
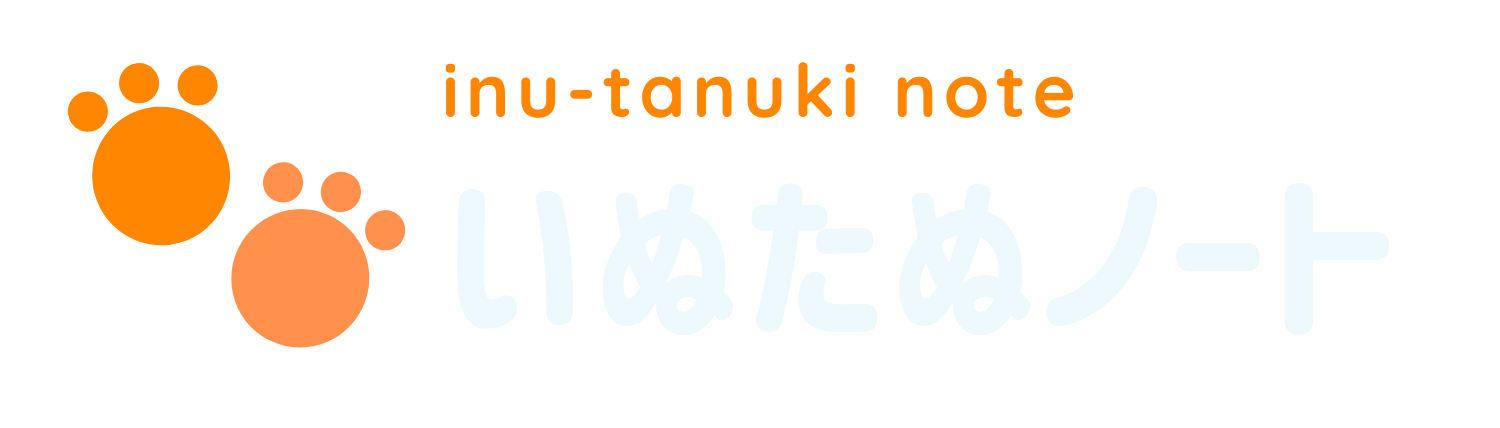
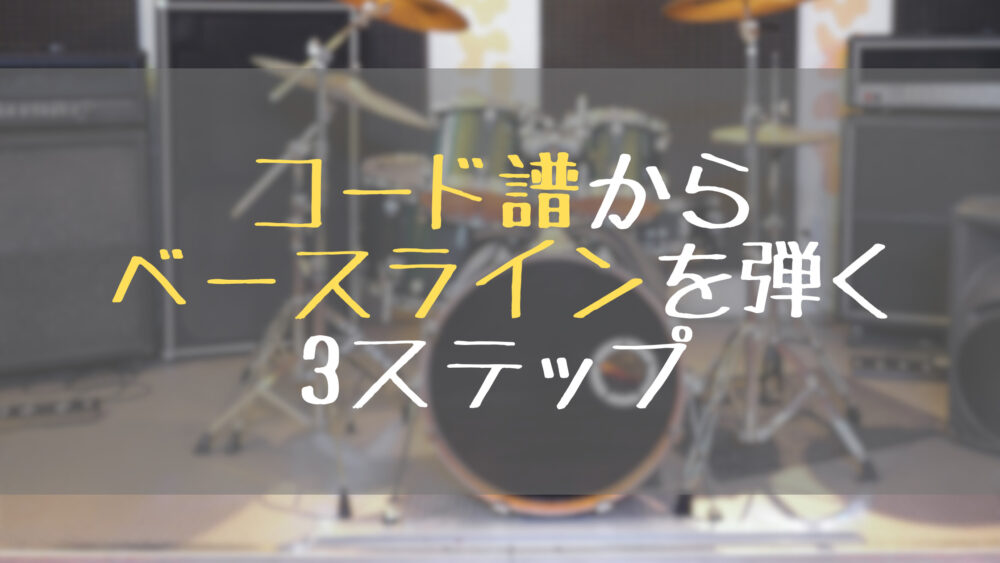


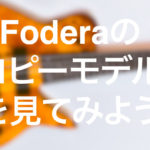
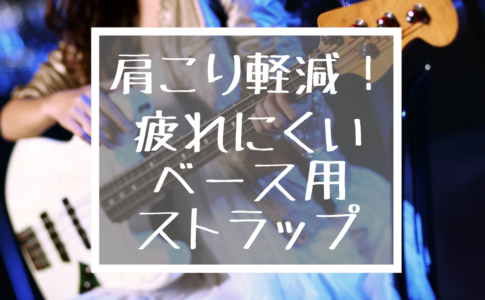
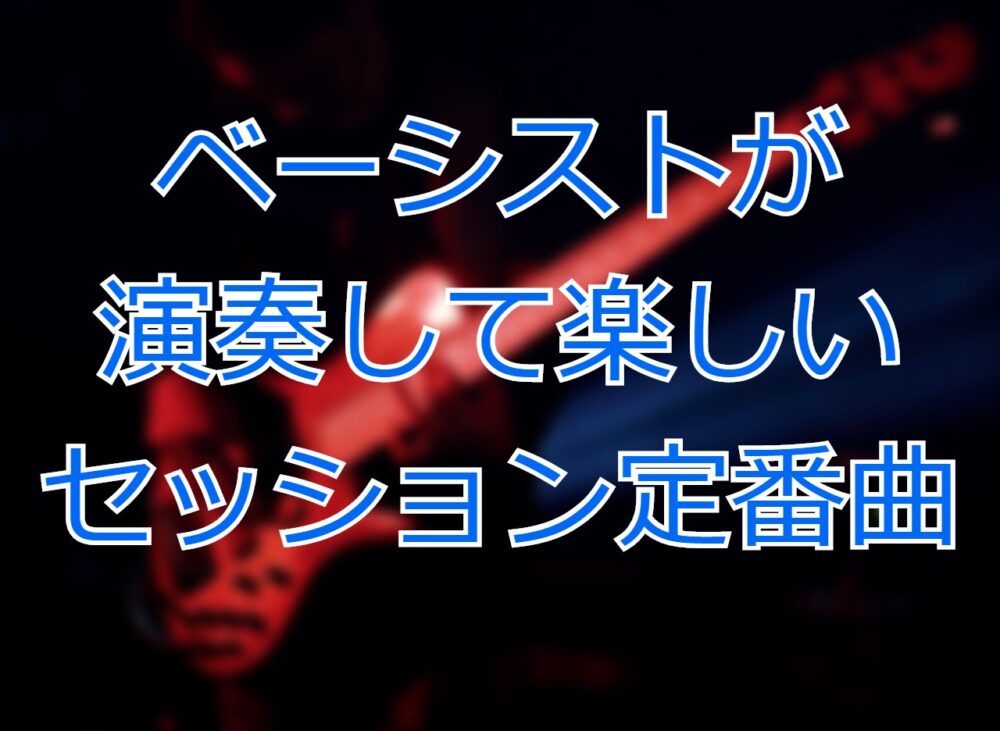
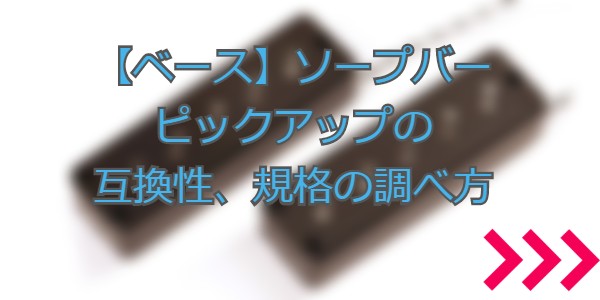

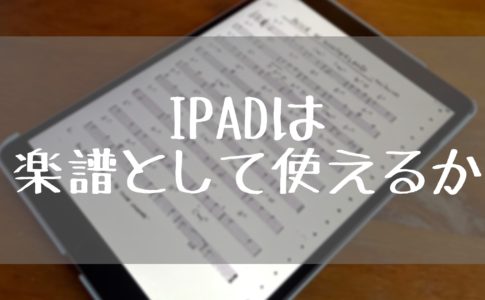
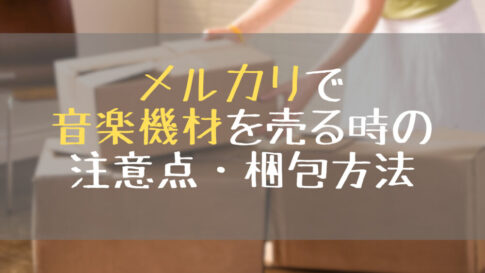

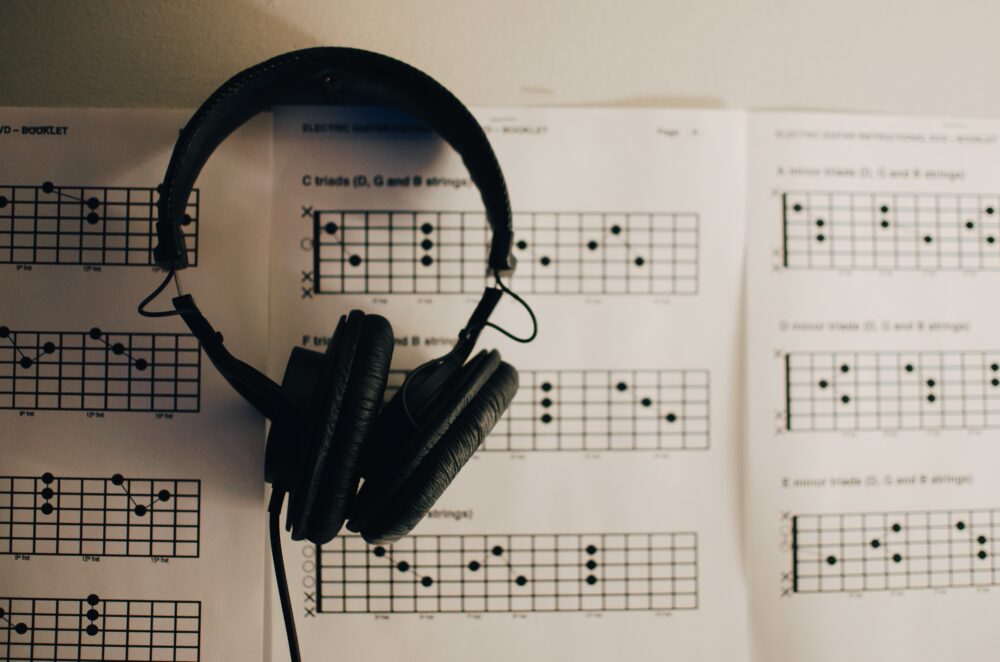


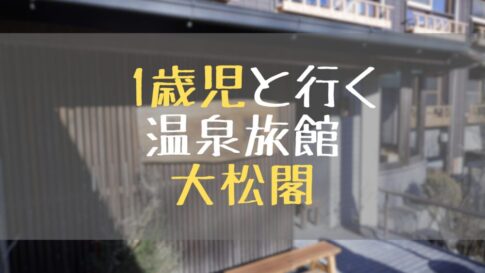
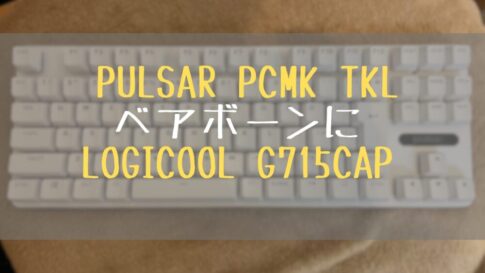



簡単なコードの知識だけでベースラインは作れます